今日は、西宮にて立志政経舎第三期のインターン説明会。

代表の今村西宮市議から全体の説明。
日本のリーダーを育成するインターンにしたいという想いを伝えてもらいました!

次はグループに分かれて学生からの質問をうけます。
やはり『なぜ、政治家になったのか?』は誰からも聞かれます(笑)
最終の選考会まで残ったのは一人でしたが、なかなか勢いのある学生で、久しぶりに頼もしく感じました。
早く、次の政治活動を本腰入れてやっていきたいです。
半年空くとなまってきます。
iPhoneからの投稿
ブログ |
橋下市長の発言がとりだたされ、不適切な部分のみが叩かれたかが、
彼の発言の中には、以下のような問題を指摘した部分がある。
なぜ、日本のメディアはこうした部分をもっと国民に伝えないのか?
こうした知識が国民にないと、日本だけが悪かったのだと国民が感じてしまう。
アメリカ人は謝ったのか? 韓国人は?ロシア人は?中国人は?
日本人の正直さや慈愛の精神につけこんで、
自分たちの歴史は棚に上げ、何を政治カードに使うのだ。
日本のマスコミはもっとしっかり、公正に報道してほしい。
軍エリートの門出に警鐘 性犯罪深刻化で米政権
2013.5.26 10:00
米軍内で性犯罪が深刻化する中、オバマ大統領とヘーゲル国防長官が24、25の両日、士官学校の卒業式で警鐘を鳴らす演説を行った。米軍の将来を担うエリートの門出に贈る言葉だけに、米政府の危機感をあらためて浮き彫りにした形だ。
オバマ氏は24日、メリーランド州アナポリスの海軍士官学校卒業式で「性的暴行を行う者は単に罪を犯すだけでなく、軍の強さを支える信頼と規律を危険にさらしている」と強調した。
ヘーゲル氏も25日に行われたニューヨーク州ウエストポイントの陸軍士官学校卒業式で「性的な嫌がらせや暴行は深刻な裏切り行為だ。この悪疫は根絶しなくてはならない」と訴えた。
米軍では最近、悪質な性犯罪が相次ぎ、ウエストポイントでも教官によるシャワー室の盗撮が発覚したばかり。米兵が関与した性的暴行の報告数も急増しており、米政府は綱紀粛正に向けた対策を迫られている。(共同)
ライダイハン 韓国軍の戦争犯罪 大虐殺と強姦
ブログ |
こうした取り組みは進めていってもらいたいですね。
語学などもどんどんやってもらわねばなりません。
私も英語教育の推進には賛成です。
しかし、、
グローバル人材を育成するのに一番大切な
大和魂を育む教育に全然スポットが当たらない。
これはおかしい。
日本の歴史文化や伝統、先人の偉業を知らない人間にいくら外国語を教えたってまったくグローバル人材ではないのです。
それを踏まえたグローバル人材の教育でなければ意味がない。
海外に出て、成功しお金を稼いで、外資系会社のために働く人材を育てて国益にかないますか?
我々の税金でやる必要がありますか?
教育は国家100年の大計でなければならないのです。
国際バカロレア 導入へ協議会
5月28日 16時25分 NHK
世界各国の大学入学資格を取得できる教育プログラム、「国際バカロレア」の導入を検討している高校などが協議会を設立し、国際的に活躍できる人材の育成に向けて連携していくことになりました。
「国際バカロレア International Baccalaureate」は、母国語以外の授業はすべて英語やフランス語などで行う世界共通の教育プログラムで、最終試験に合格すると各国の大学入学資格を取得することができ、現在、国内では16の高校などが取り入れています。
協議会は、プログラムに関心をもつ全国およそ70の高校や教育委員会などが導入に向けた課題などを検討するため設立したものです。東京・千代田区の会場では、呼びかけを行った東京学芸大学の村松泰子学長が「入学資格を与えるだけでなく、グローバルな人材をどう育成していくかが問われている」とあいさつしました。
「国際バカロレア」については、政府の教育再生実行会議が国際的に活躍できる人材の育成に向けて、プログラムを導入する学校を今後5年間で200校に増やすよう提言していて、国は導入を促すため授業の一部を日本語で行っても同じ資格を得られるよう準備を進めています。
28日の会議では、日本語の教材の開発や指導できる教員の養成、情報発信などが課題だとして、今後連携して取り組んでいくことを決めました。
国際バカロレア資格:都立国際高が認定取得へ 公立で全国初 /東京
毎日新聞 2013年03月16日 地方版
都教委は15日、海外の大学に進学しやすくなる「国際バカロレア(IB)資格」の認定取得を都立国際高校(目黒区)で目指すことを明らかにした。公立高では全国初となり、3~4年後の取得を目標にする。都議会文教委員会で山崎一輝議員(自民)の質問に直原裕・都立学校教育部長が答えた。
IBは国際的に認められている大学入学資格の一つ。スイスに本部がある国際バカロレア機構の定めるカリキュラムを修了すると統一試験が受けられ、点数によって海外の大学の入学資格が得られる。カリキュラムは高校2、3年の国語以外の6教科(数学、理科、芸術など)の授業を英語で行うとされており、国内の高校では私立5校しか認定を受けていない。
都教委は13年度、国際高の管理職も加えた検討委員会を設置し、取得に向けてのスケジュールや生徒数を協議する。担当者は「英語以外の教科担任で英語が堪能な教員を見つけることが急務。国際的に活躍する人材を育てる教育環境を整えたい」と話している。【柳澤一男】
学長主導の大学改革後押し 教育再生提言 教授会の権限縮小
産経新聞 5月29日(水)7時55分配信
政府の教育再生実行会議(鎌田薫座長)の第3次提言は、2つの安倍カラーが出た。一つは大学教育のグローバル化、もう一つは伝統教育の重視だ。特に、「大学自治」を振りかざして大学改革に消極的な教授会については、役割を厳格にすることで、学長主導の大学改革を後押しする狙いがある。
教授会は、カリキュラムの設定、学生の処分や入退学の決定、教授の採用に深くかかわり、大学の運営に存在感を示してきた。学校教育法には「大学には重要な事項を審議するため教授会を置かなければならない」とあり、ある大学関係者は「『重要事項』を拡大解釈して大学を事実上支配してきた」と説明する。
提言は、「教授会の役割を明確化し、学校教育法等の法令改正の検討や学内規定の見直しも含め、抜本的なガバナンス改革を行う」とした。教授会の権限を弱めることを通じ、グローバル化や組織改革で大学の生き残りを図ろうとする学長がリーダーシップを発揮しやすい環境を整備する狙いがある。今後、教授会を学長への助言機関に変えることなどが想定される。
また、鎌田座長は28日、首相官邸で記者団に「(提言では)日本人としてのアイデンティティー確立や日本文化発信に関する記述を強化した」と説明した。
提言は、真の国際人は外国語で日本の文化を紹介できる人物であるとの基本理念を打ち出した。
その上で、小中高校を通じて「国語教育やわが国の伝統・文化についての理解を深める取組を充実する」と明記した。英語で日本史や茶道を学ぶことが想定される。素案の段階にはなかった「日本文化について指導・紹介できる人材の育成や指導プログラムの開発等の取組を推進する」との記述も加えた。(内藤慎二)
ブログ |
今日も早朝からミーティングをしてきました。
テーマは、G1東松龍盛塾について。
四月のプレイベントの総括と今後の運営について、
グロービスの掘氏、
ジャストギビングの佐藤氏、
青山社中の朝比奈氏、
三重県知事の鈴木氏、
龍馬プロジェクトからは私と長野氏、
といった面々で構想をまとめてきました。

皆さん、視野が広く実績のある方ばかりで、非常に有意義なミーティングになります。
秋からの本格始動に向けて、
詳細をまとめていきます。
0から1を創るのは、やり甲斐があります!
iPhoneからの投稿
ブログ |
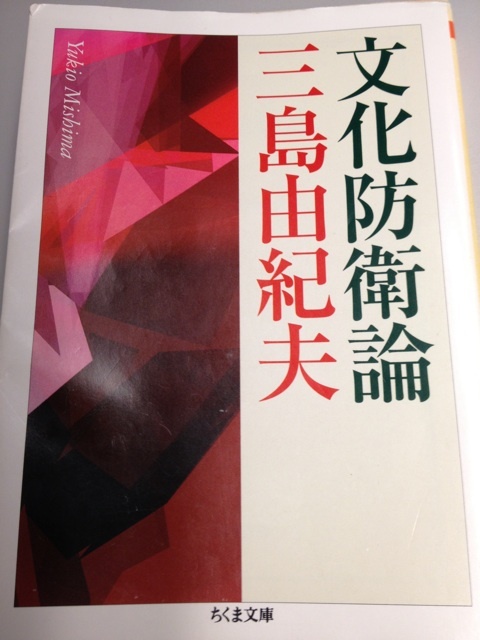
カンボジアへの行き帰りの時間を利用し、先月ある先生に進めて頂いた『文化防衛論』を読みました。
三島由紀夫氏の本は文学作品を主に読んでいて、こうした類の本は難しくて、また、古い議論だと思っていたのであまり読んでいませんでした。
しかし、憲法改正が議論されつつある今日、三島氏の主張は決して古い議論ではなく、今憲法を考えるからこそ読まれるべき作品であり、
三島氏の作品に限らず、こうした知識ベースを国民が共有しないと、国民主権という錦の御旗の下に憲法を国民投票で決めていいのか、とすら感じました。
作品の中の文言を抜き出すと、
人間性と政治秩序との間の妥協こそが民主主義の本質
天皇の権限よりも、天皇というものを一種の文化、国民の文化共同体の中心として据えるような政治形態にすべき
言論の自由が大切ー
我々が文学をやっているということは一人一人がヒトラーであり、一人一人が毛沢東である。
ブルジョア新聞ー朝日新聞など
秩序を守るためならイデオロギーなんかどうでもいいから、秩序を守るものとして現れたものなら誰の手にでもすがりつく
護るべきものー
自分の人間としての誇りを護ることが文化を護ること
文化を護るために死ぬのであり、その文化の象徴が天皇の役割であった
などが印象に残ります。
三島氏の理論でいくと多くの日本人は守るべきものもわからず、自分を失ってしまっていますね。
という私もいろいろ勉強を重ね、
彼の言葉の意味がやっとわかるのです。
現代の大衆に政治家として訴えても、全く響かないテーマでしょうが、
政治家としては腹に落としておくイデオロギーの詰まった本でした。
こうした話が議論でき、またそこから政治を考える場として龍馬プロジェクトをつくったんです。
ですから、龍馬プロジェクトって何って、一言では説明しがたいのです。
iPhoneからの投稿