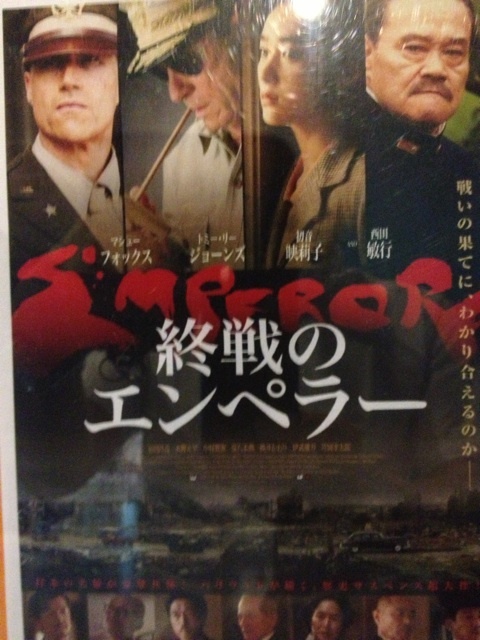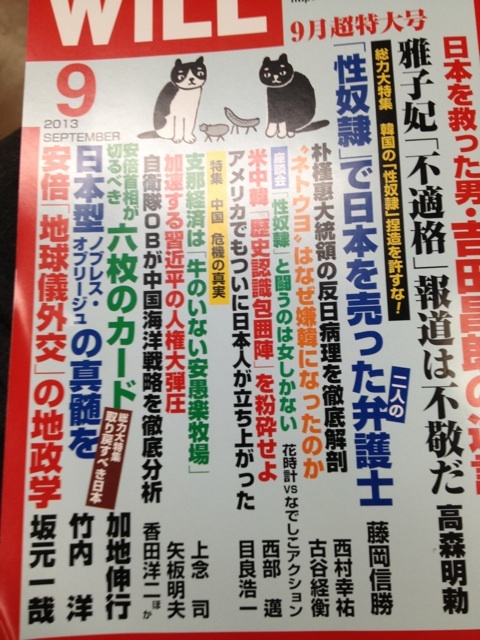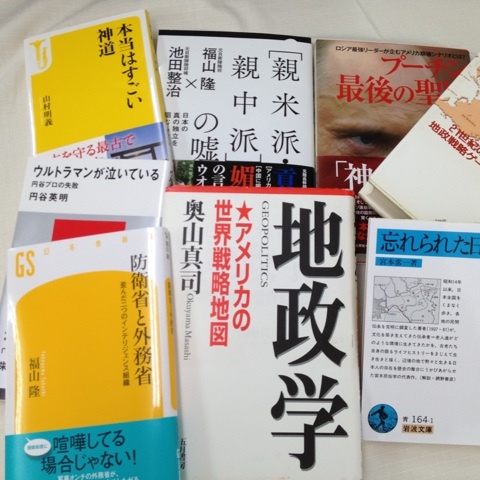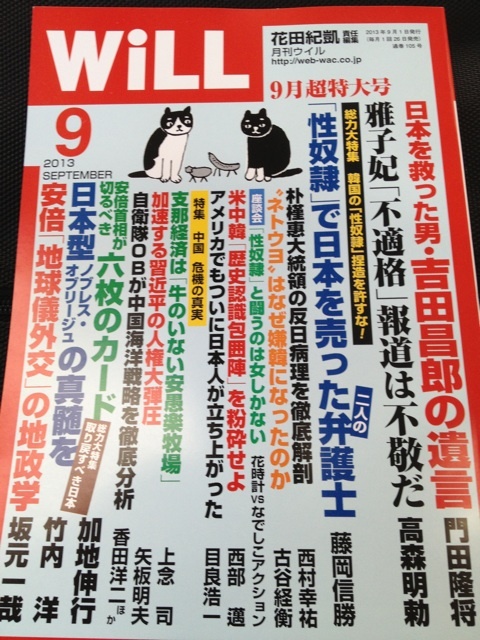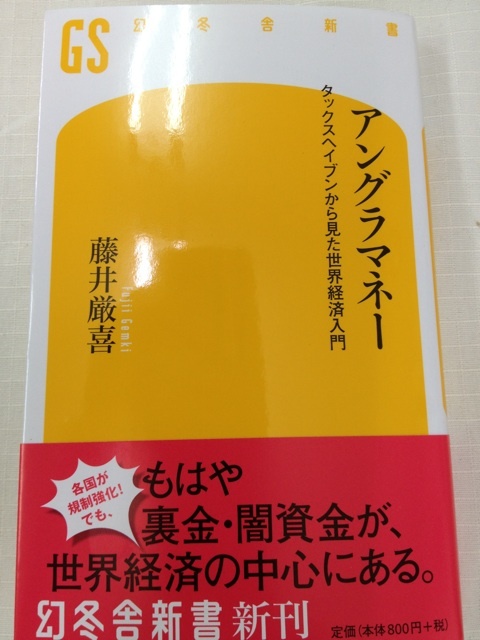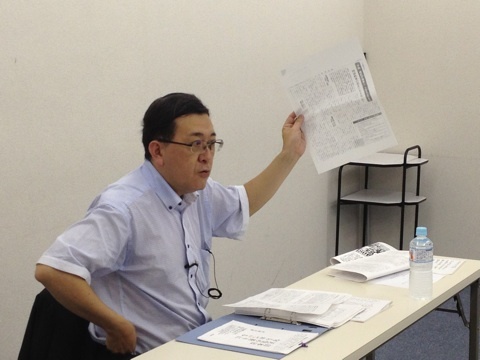歴史が変わり、生き証人がいなくなってくるとこうして歴史の表記も変えられていくのですね。
歴史は記すものではなく、つくるものだ、という意見を聞いたことがありますが、
こうした動きをみると納得のいくところもあります。
50年後の台湾人も親日でいてくれるでしょうか。
今を生きる日本人の努力が求められているように感じます。
台湾、日本統治時代を「支配」表記に
2013.7.24 10:27 産経
【台北=吉村剛史】台湾の行政院(内閣に相当)は22日、日本が台湾を領有した時代について、公文書上の表記を、日本による支配などを意味する「日據(にっきょ)」に統一することを決め、各機関に通達した。小中高の教科書では現在、「日治」(日本の統治)という表記が一般的だが、「日據」の表記も認められる。
地元メディアによると、日清戦争後の下関条約で清から台湾の割譲を受けた日本の統治時代(1895~1945年)に関し、一部の民間出版社が今年、「日據」と表記した高校歴史教科書を申請。これに有識者らが「日治」などに改めるよう求めていたが、教育部(文科省)は「学問の自由」を理由にいずれの表記も容認。行政院も「教育部の決定を尊重」するとともに、公文書上は「日據」に統一することを決めた。
戦後の台湾では「日據」が主流だったが、李登輝政権下で、日本の台湾領有時代を肯定的に評価する動きもあり、教科書では「日治」や「日本統治時期」との表記が定着していた。
野党は今回の行政院の通達について、馬英九政権の対中協調政策の一環とみて「中国的視点に基づく決定だ」と反発している。
対中融和で台湾が教科書表記を議論
2012.7.1 12:00[国際情勢分析]
2期目の馬英九(ば・えいきゅう)政権が始動した台湾で、9月の新学期から使用する学校教科書の中国と台湾の呼称表記に関する基準を明確化しようという動きが浮上し、波紋を広げている。中国との関係改善を進める馬政権の対中姿勢のあらわれとみられるが、従来あいまいだった「主権」などにかかわる聖域に踏み込み、線引きする作業となるため、野党側からは「脱台湾化を促す」「多元社会の台湾で中華文化主体に偏るべきではない」との懸念も示されている。
「台湾」表記はしない
台湾の教育部(文科省に相当)による中台呼称の基準原則設定の動きは6月10日、最大野党・民主進歩党所属の鄭麗君・立法委員(43)=国会議員に相当=の指摘で明らかになった。
教育部や鄭委員らによると、現在議論されているのは、9月に入学する高校1年生の歴史教科書での中台の表記や用法、中台関係論の経緯など。
すでに教育部が5月4日、出版社に示した小中学校社会科系教科書での要望基準では、主権に関わる記述で、(1)「中華民国」の代用表現として「台湾」を用いない(2)同様に「中華人民共和国」に代用表現に「中国」を使用せず、代名詞としては「中国大陸」「大陸地区」「中共」などとする。一方、地理や経済、文化上の区別表現としては、(3)「台湾」と「中国大陸」とし、さらに(4)両岸(中台)人民関係条例に関する場合は「大陸地区」「台湾地区」と表現する-などとされた。
高校1年の歴史に関しては、さらに台湾の国際的地位に関して「未定論」には触れず、「台湾が中華民国に属する事実」を明確にし、1945年以降、国際社会でこれに「異議のない」ことを説明することにも、踏み込んで話し合われているという。
「中華文化が中心」
他にも李登輝政権時代の「特殊な国と国の関係」や、陳水扁時代の「一辺一国」(台湾と中国は別々の国)、馬政権での「一中各表」(一つの中国を各自が示す)を「中華民国憲法」に沿って説明することも俎上に。また、台湾の政治や経済の発展については、政党の果たした役割を重視し、一面的な記述を戒め、戒厳令期の時代背景や地方自治の成果なども強調。台湾の多元的な文化に触れる際は、「中華文化が中心」で、移民社会では「漢民族が主流で、中国人と中華文化が主流である事実を明確化する」ことなどをあげている。
教育部では7月中にまとめるとしているが、この歴史教科書に関しては、3、4月に審査を終えたとされている。5月以降、審査機関を通じて改めて検討が加えられていることについて、野党議員らは、与党・中国国民党(国民党)の元老格である郝柏村・元行政院長(92)が今年2月、「現行の教科書は台湾独立色が強い」として、同様の意見を台湾の有力紙に投書したことや、5月に行われた審査機関の一部委員の「不自然な交代」がきっかけになった、とも指摘している。
支持、評価、疑念の中で
いずれにしても馬英九総統(61)が5月20日の2期目の就任演説で主張した通り、中台が「相互の主権を承認せず、相互の統治権を否認せず」とした対中姿勢の社会的合意形成や、「一つの中華民国、二つの地区(大陸地区と台湾地区)」を徹底する意図が垣間見られる内容で、「中華民国」の存在を前面に出す一方、従来回避されてきた「中華人民共和国」にも向き合う姿勢だ。
この動きを受けて、中国国務院台湾事務弁公室の報道官は13日、台湾での教科書の中台表記の基準原則見直しは、「ひずみを正す行為」として支持を表明した。
識者からは「中華民国憲法に沿って現状維持を補強する」との見方がある一方、「多元社会の台湾では中華文化と台湾文化は並列の関係で主従はない」とする意見までさまざまだ。
李登輝政権時代の1997年以降、中学の地理・歴史・社会の教科書として台湾史に焦点をあてた「認識台湾」や、陳水扁政権時代の「台湾正名運動」の流れを断ち切る「脱台湾化」が狙いとの疑念も出ており、出版社側は、こうした論議を見すえつつ、並行して教科書の編集を進めている。
与野党の意見衝突がそのまま持ち込まれたかのような議論の中、新たな高校1年生が、9月以降どのような中台関係の形を学校で学ぶことになるのかが注目されている。
(よしむら・たけし 台北支局)