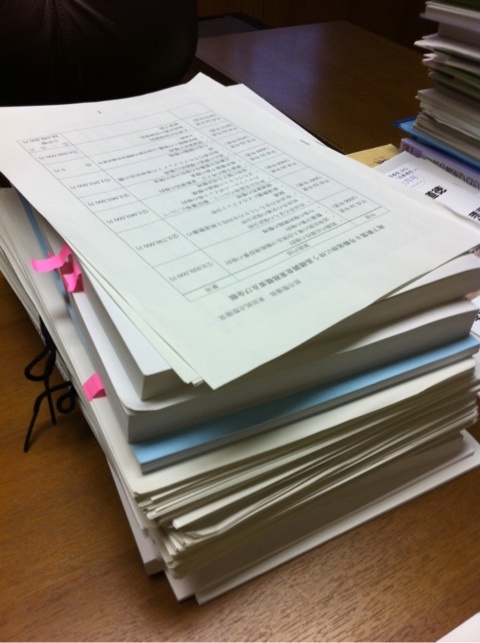私も安易な選択制には反対しています。
市内に先進的なモデル校を作って、その学校のみ学区を廃し、市内全域から通えるようにするということは考えています。
しかし、記事の中にもあるように、しっかりした構想と予算がなければモデル校も作れません。
今の吹田市政の状況では、教育に光が当てられることは当分なさそうです、、、(泣)
学校選択制見直す動き・・・特定校に希望者集中(東京多摩)
子どもが通学する小中学校を選べる「学校選択制」を巡り、多摩市は2013年度から選択の条件を制限し、見直す方針を固めた。制度導入から10年余り、全国的にも見直しの動きが進んでおり、専門家は「大規模校に人気が集まるばかりで、公立学校間で教育内容を競い合う資源や仕組みがない」と指摘する。
■多摩市は条件制限
公立の小中学校は通学区域の「指定校」に通うのが長年の仕組みだったが、1997年に国が通学区域の弾力運用を打ち出したことがきっかけで、2000年以降、選択制が全国に広がった。〈1〉市区町村内の学校を自由に選べる〈2〉地域で分けたブロック内で選べる〈3〉指定校はあるが隣接校への通学が可能――などのタイプがある。都教育委員会によると、都内では中学で19区10市、小学校で15区8市で実施されている。
多摩市では「教育水準の向上」「特色ある教育づくり」を目指して03年度から導入。小学校では隣接区域から、中学校では市内全域から選ぶことができ、小学校で平均6・7%、中学校で同10・1%の児童生徒が、制度を利用していた。
しかし特定の学校に希望者が集中し、学校規模の格差が拡大。区域内に住む生徒数はほぼ同じなのに、隣接する二つの中学校の一方に、他方の倍以上の生徒が集まるケースも。大規模校は部活動や行事が活発になり、ますます人気が高まり、小規模校は年々生徒が減ってしまうといった、悪循環が浮き彫りになった。
また生徒の居住地域が広域化し、学校と保護者、地域のつながりが薄れたといった声や、東日本大震災の発生を受け、遠方から通う生徒の登下校時の安全確保を懸念する声も出ていた。
このため市は先月、制度の大幅見直しの素案をまとめた。指定校への通学を原則とした上で、区域外に通うことができるのは、通学に30分以上かかり(小学生で1・5キロ以上、中学生で2キロ以上)、隣接校に通うことで通学時間を半減できる場合など、特例とすることにした。市は「地域のつながりの核として、改めて学校を位置づけたい」とし、3月末には正式決定する予定。13日までパブリックコメントを実施し、市民からの意見を募っている。
学校選択制に詳しい国立教育政策研究所(千代田区)の葉養(はよう)正明教育政策・評価研究部長は「現状の学校選択制では、子どもが大規模校に集まるケースが多い。自治体は選択制を導入するだけでなく、各校が特色を出せるだけの予算や、教育プログラム、評価システムをつくることが必要」と語る。
■全国でも相次ぐ
学校選択制を見直す動きは、全国でも相次いでいる。前橋市は11年度から、都内では江東区が09年度から、学校間の人数格差や地域との関係の希薄化を理由に、選択の条件を狭めた。長崎市は11年度末で小中学校の選択制を廃止、長野市は12年度末で小学校の選択制を終了させる方針で、新宿・江戸川区でも、見直しに向けた検討が行われている。
森上教育研究所(千代田区)の森上展安代表は「平均的な教育が求められる公立校では、教育内容で競い合える資源や仕組みがなく、選択制の導入は準備不足だったのでは」と話す。「代わり映えのしない教育内容では、保護者や生徒は選ぶ基準が見いだせず、部活動や生活の利便性などで選ぶしかない。自治体は、まずは地域の実情に沿った教育ニーズをくみあげることが必要」と話している。
(2012年3月6日 読売新聞)