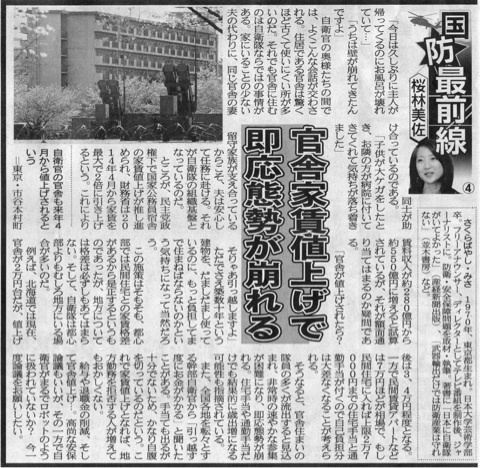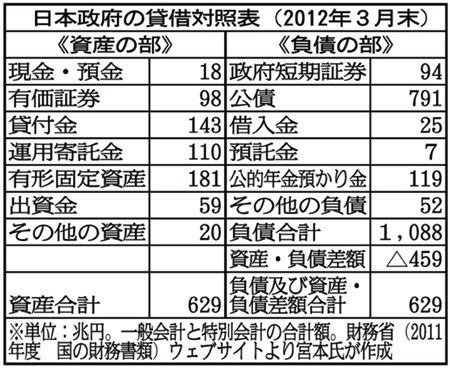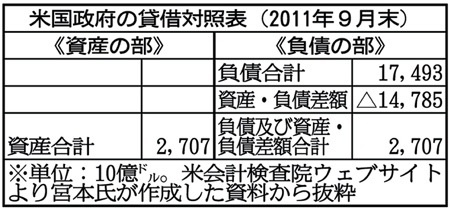またまたちょうど訓練にきている時にこんなニュース。
永世中立国で知られるスイスは、
非武装中立ではなく、武装中立の国。
ここでも徴兵制廃止の議論がありましたが、否決されるようです。
記事では、伝統だから、、みたいにかかれていますが、それだけのはずはありません。
大阪府ほどの人口のスイスが、ヨーロッパの強国の中で生き延びるためには、一人一人が国を守る気概を持たねばならないのであり、
その心を鍛える徴兵なのではないかと私は考えています。
私は日本で、徴兵をやることに反対ではありませんが、
そんなことをしたら自衛隊がキャパオーバーでパンクしてしまうかもしれませんし、隊全体の練度が下がり、国防上よくない気がします。
しかし、若者が家を出て、数ヶ月でも強制性のある生活をする機会は是非つくるべきです。
それは、防災訓練でもいいし、ボランティア合宿でも構いません。
自由を奪われ、団体で生活することの大切さや、戦争に行かれた先人の大変さがわかれば、それでいいのです。
今の日本に暮らせることの有難さや自由の大切さ、平和の有り難み、自分の適性などを
周りの助けなく、自分と向き合いながら考えさせられる時間を若いうちにもつ。
これが大切だと思います。
こうしたことは、本来学校の役割でした。
しかし、今の日本の公教育はこの機能をだいぶ失ってしまった。
だから、子供のまま年だけ成人し、子供が子供も育てているケースをたくさん目にします。
私のすすめたい教育改革の軸の一つがここにあります。
揚げ足をとる人がいるので、
再度いいますが、私は徴兵をやろうといっているのではありません。
若者を大人にするトレーニングの場を国や行政が責任をもってつくるベきだ、と考えています。
そこには、自衛隊や軍隊の教育プログラムがかなり参考になると思っています。
こうした思いも私が予備自衛官を続ける動機の一つでもあります。
私も訓練が終わると、自由な日常の有難さを毎回感じますから^_^
スイス、徴兵制廃止を否決 国民投票、伝統を支持
2013.9.23 00:41 共同通信
スイスで22日、男性への徴兵制を廃止すべきかどうかを問う国民投票が行われ、地元メディアによると、廃止は反対多数で否決されることが確実となった。
国民皆兵制の武装中立を維持するスイスでは近年、「他国から現実の脅威にさらされているわけではなく金の無駄遣いだ」として徴兵制の廃止を求める声が出ているが、国民の多くが伝統的な制度を支持した形だ。
政府も国防能力を脅かすとして徴兵制廃止に反対を表明していた。
地元メディアによると、徴兵が終わった後も予備役のため銃を自宅に保管できることから、銃規制をめぐる議論も活発化している。2011年には徴兵が終わった後も自宅に銃を保管できる制度を見直すかどうかを問う国民投票が行われ、反対多数で否決された。(共同)
聖域とされるスイスの徴兵制度に廃止要求
成人男性には兵役または社会奉仕が義務となっているスイス。そんなスイスの軍事制度を根底からくつがえすかもしれない国民発議(イニシアチブ)が成立する見込みだ。
市民グループ「軍隊なきスイスを目指す会(GSoA/GSsA)」は先週木曜日、イニシアチブ成立に必要な署名数を管轄所に提出した。兵役義務の廃止を求めるこの法案は今後、連邦議会などの審議を経て国民投票にかけられる予定だ。
軍隊なきスイスを目指す会が設立されたのはおよそ30年前。1989年に初めて起こしたイニシアチブでは「軍隊の廃止」というシンプルかつ過激な要求を掲げ、これまで武装中立を貫いてきたスイスで突如世間の注目を浴びた。
スイスの憲法は、健全な男性はすべて兵役義務を負うと定めている。1996年には兵役の代わりに社会奉仕勤務ができるようになったが、実際、選択の自由は限られている。女性は任意で軍務に就くことができる。
軍隊の廃止という初めてのイニシアチブは国民投票で64%の反対で否決された。だが、第2次世界大戦後、自国軍と中立のおかげで独立を保ってきたイメージのあるスイスにとって、このイニシアチブは政治的に大波乱を呼び起こした。
軍隊なきスイスを目指す会は過去30年で五つのイニシアチブを立ち上げている。また、武器輸出禁止や新しい戦闘機購入反対を掲げ、連邦議会の決定に対して2回レファレンダム(連邦法の改正などに関し、その可否を国民投票にかける制度)を起こした。しかし、どの試みも国民投票で跳ねつけられている。
聖域に踏み込む
これまでの敗北にもめげず、軍隊なきスイスを目指す会のヨー・ラング会長は「スイスの近代史は我々抜きで語れない」といたって楽観的だ。同会は軍隊を批判したり、軍隊に対する世間一般の考えに疑問を投げかけたりと、聖域とされる政治分野に足を踏み入れたと自負している。
軍隊なきスイスを目指す会はまた、軍隊の規模縮小や軍事費削減を訴えてきた。社会奉仕勤務の導入を推進するなど、軍隊がより人道的な方向に進むための活動もしてきた。
さらに過去10年間、スイスで繰り広げられた平和運動を引っ張ってきた。だが、同会の活動はそれだけにとどまらないとラング氏は主張する。種々の国民発議成立に向けた署名活動では、この5年間で総計50万人分を集め、直接民主制で中心的な役割を担ったと語る。
そのうえ、国民投票での敗北は必ずしも政治的敗北ではないと話すのは同会庶務課のヨーナス・チュルヒャー氏だ。繰り返し訴え続ければ、いつかは報われると語る。
両氏によるとここ数年、軍隊なきスイスを目指す会は武器輸出禁止や一般家庭での武器保管といった具体的な問題に関わるなど、現実問題に目を向けているという。
行き詰まり
一方、スイス軍存続を擁護する団体もある。現役・退役軍人から成る「ジアルディーノ・グループ(Gruppe Giardino)」は、「軍隊なきスイスを目指す会はここ30年間、軍隊のない社会という幻想を追い続けている」と批判する。
ジアルディーノ・グループのハンス・ズーター会長は「徴兵制度の撤廃を求めるのは新マルクス主義の思想と一致する」と言い放つ。さらに、平和主義者の行う「非スイス的」で「軍隊に反対する」活動はこの30年間全く変わっておらず、平和主義者は「新マルクス主義と階級闘争のわだちには