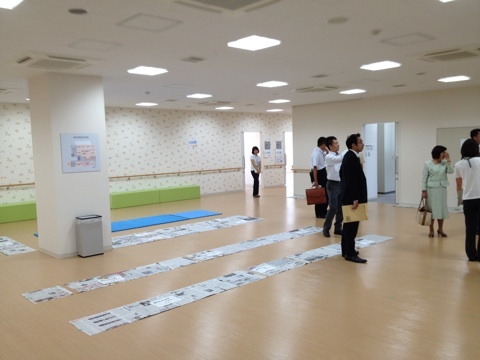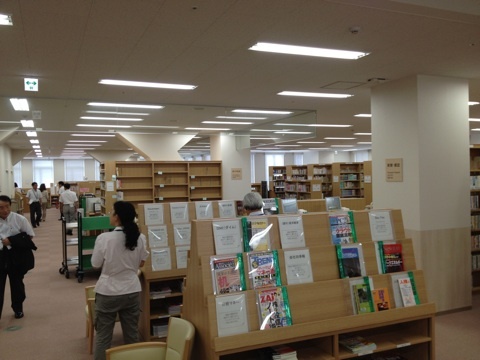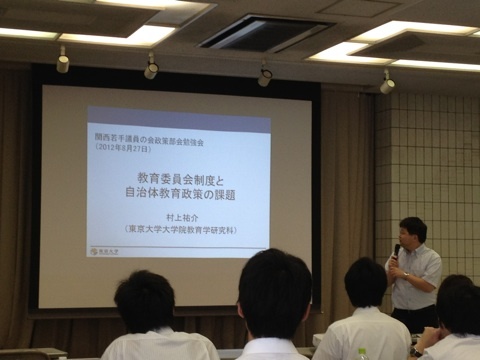宮澤氏の活躍していた頃には、
日本には圧倒的な経済的優位性があり、
表向き謝っておけば、向こうの政治家の顔がたち、摩擦をさけることが出来ました。
余裕があったのでしょう。
しかし、今はもう余裕をかましてはいられません。
本気で怒らないと本当に国がダメになります。
過去の踏襲はもう十分です。
今の国情や世論にそった外交をお願いします。
その代わり、自分たちの主張をするには国民にも覚悟が必要です。
政治家だけの覚悟ではいけません。
—————–
8月26日 産経抄
「一犬虚に吠(ほ)ゆれば万犬実を伝う」ということわざがある。「虚に」が「影に」となるなど変形は多いが、意味は同じだ。犬の吠え方がそうであるように、一人がいいかげんなことを言い出すとまるで本当のことのように広まってしまう。そんな時に使う。
▼上智大教授だった渡部昇一氏が雑誌『諸君!』などで「萬犬虚に吠えた」と当時の教科書騒動を批判したのは昭和57年9月のことだ。約2カ月前、文部省が教科書の「日本軍が(中国)華北に侵略」を「進出」に書き換えさせたとマスコミがいっせいに報じた。そこから起きた問題である。
▼実はこの報道は完全な誤報で、書き換えの事実はなかった。ところが誤報が独り歩きし、中国や韓国が抗議する。8月26日には宮沢喜一官房長官が教科書検定では「近隣諸国に配慮する」とする談話まで発表した。渡部氏はそのことを批判したのだった。
▼誤報をしたうえ、産経新聞以外きちんと訂正もしなかったマスコミの罪は大きい。だが誤報と知っていながら、中・韓の抗議を唯々諾々と受け入れた当時の鈴木善幸内閣の責任はもっと重い。その後の両国に日本攻撃の糸口を与えたからだ。
▼悪名高きこの「宮沢談話」は30年がたった今も威力十分である。特に韓国は竹島の不法占拠を慰安婦問題とからめ正当化しようとする。歴史問題を持ち出せば日本の政府やマスコミは必ず黙り、屈服する。30年前に味をしめ、そう思っていることは間違いない。
▼野田佳彦首相は記者会見で「竹島問題は歴史認識の文脈で論じるべきでない」と述べた。それなら「宮沢談話」も慰安婦問題で韓国側の主張に沿った「河野談話」も「見直す」と言うぐらいの気迫を見せてほしい。
宮沢談話30年 謝罪外交の連鎖断ち切れ
2012.8.26 主張
歴史教科書問題で中国や韓国の要求を一方的に受け入れた宮沢喜一官房長官(当時)談話が発表されて30年になる。近隣諸国には謝れば済むというあしき前例となり、今日の対中・対韓外交にも尾を引いている。
香港の活動家が尖閣諸島に不法上陸した事件で活動家が日本の巡視船にれんがを投げつけるなどの暴力行為があったのに、厳正な刑事手続きをとらず、活動家を香港に強制送還した。対中配慮を際立たせたのも、謝罪外交の一例である。
李明博韓国大統領が竹島上陸を強行し、天皇陛下に謝罪を求めた問題でも、日本側が十分な対抗措置をとっているとは言い難い。李大統領が再三、蒸し返している慰安婦問題にも、日本政府は有効な反論を加えていない。
そもそも、昭和57年8月の宮沢談話は日本のマスコミの誤報が発端だった。同年6月、新聞・テレビは、旧文部省の検定により、日本の中国「侵略」が「進出」に書き換えられたと一斉に報じた。
中韓両国はこの報道をもとに、外交ルートを通じて日本政府に抗議してきた。だが、そのような書き換えの事実はなかった。
にもかかわらず、「政府の責任で教科書の記述を是正する」「検定基準を改め、近隣諸国との友好・親善に配慮する」と両国に約束したのが宮沢談話である。
これを受けて、教科書検定基準にいわゆる「近隣諸国条項」が追加されたため、中国や韓国におもねるような教科書記述が急激に増えたことは記憶に新しい。
当時、産経新聞は誤報を読者に謝罪したが、他紙は黙殺か弁明で終わっている。改めてマスコミの真摯(しんし)な反省が必要である。
日本がただ謝罪するだけの近隣外交はその後も続いた。
平成5年8月、宮沢内閣は日本の軍や官憲が慰安婦を強制連行したとする証拠がないのに、強制連行を認める河野洋平官房長官談話を発表した。戦後50年の7年8月には、「遠くない過去の一時期、国策を誤り」と決めつけ、「植民地支配と侵略」をわびた村山富市首相談話が唐突に出された。
これらの歪(ゆが)んだ政府見解が歴代内閣の外交をどれだけ萎縮させたか計り知れない。その結果、今回の韓国大統領のあまりに非礼な言動を招いたともいえる。
野田佳彦政権は積年の謝罪外交の連鎖を断ち切るべきだ。
iPhoneからの投稿