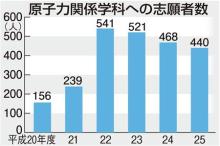主権回復の日については、先週沖縄1区の国場さんともお話をしました。
沖縄の方々すれば、5月15日がまさに主権回復の日となるでしょう。
私は、4月28日でも5月15日でも、意見の違いをまとめて1本化すべきだと考えます。
別々に2回式典などを行うのはなんだか本旨でないような気がします。
もっといえば、日本に国防軍ができ、在日米軍がいなくなったときが、本当の主権回復の日かもしれません。
主権回復の日には、ただ主権の回復を喜ぶのではなく
主権がなくなるとどうなるのか、
どんな統治があったのか、
主権を守るために先人はどう戦ったのか、
などをしっかり国民が考える日にしなければならないと思います。
いつにするかより、その日に何をするか、そんな議論を聞きたいと思います。
沖縄返還式典で配慮の意向=安倍首相
安倍晋三首相は5日の衆院予算委員会で、1972年5月15日の沖縄本土復帰を記念
して政府が節目ごとに開催している式典について「どういうタイミングでやるか、当然考
えなければならない」と述べた。サンフランシスコ条約発効後も米国施政下に置かれた沖
縄などが、発効61年目の今月28日に政府が開く「主権回復の日」式典に反発している
ことを踏まえ、より沖縄に配慮した形での復帰記念式典の開催を検討していく考えとみら
れる。
民主党の細野豪志幹事長が「沖縄が本土に復帰した時が、本当に日本が独立した日だ」
と強調、主権回復の日の式典に匹敵する行事を5月15日にも開催するよう求めたのに答
えた。
(「時事通信」 4月5日17時34分配信)