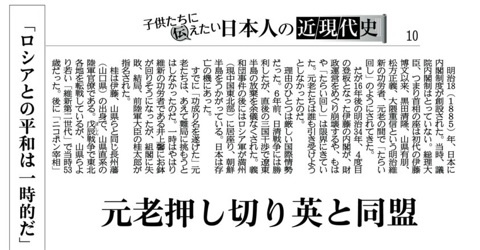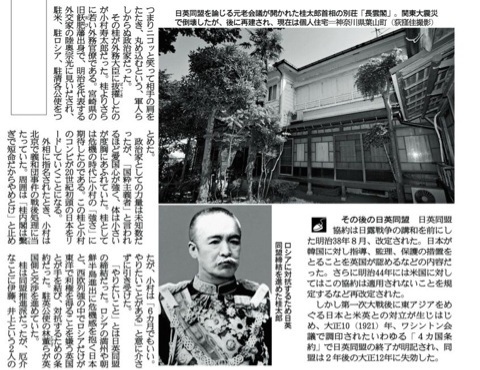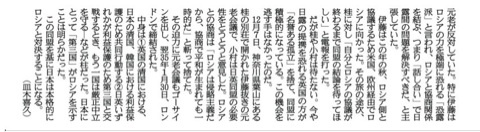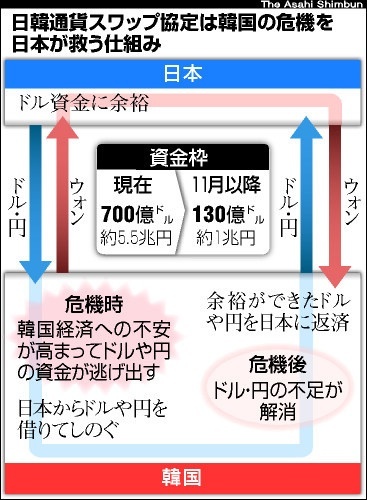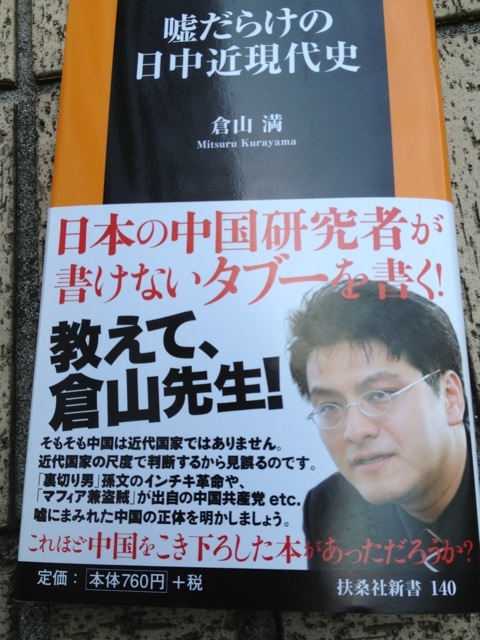私が秋山氏と同じ時代に生まれていてもあまり仲良くはならなかったと感じます。
彼はあまりに厳格過ぎますf^_^;
しかし、尊敬はしたと思います。
私も人生の最後は教育に関わって死にたいと思っています。
「何でも奉公させてもらうよ」
といえるくらい、自分を磨いていきたいと思い、秋山氏の生き様から学びます。

【忘れ難き偉人伝】
秋山好古(上)
「何でも奉公させてもらうよ」
2013.5.25 09:15
大正13(1924)年4月7日午前7時前、松山の私立北予中学校の校門前で生徒が知らない男が笑顔で会釈していた。
「あの愛想のええ、変なおやじはだれぞな」。生徒たちはささやき合う。7時45分、講堂に集められた生徒たちは壇上に上がった新任校長を見て仰天する。さきほどのおやじだった。
「おはよう、生徒諸君。私が今度、校長になった秋山好古だ。私は前校長から2つの宝物を預かった。ひとつは若き鳳凰(ほうおう)である諸君たちであり、もうひとつはその若鳥を育て上げる巣箱であるこの校舎だ。私はこの2つの宝物をさらに磨き上げ、お国への報恩感謝の標(しるし)としたい」
学校は歩兵第22連隊に隣接しているため、軍人は見慣れているが、連隊長でも陸軍大佐であり、将官を見る機会もない。まして日露戦争の英雄で、陸軍大将だった秋山好古(1859~1930年)の突然の帰郷は周囲を驚かせた。
好古は同9年12月、教育総監を任命された。陸軍将兵教育の最高職で師範学校出身の好古らしい陸軍最後のお役目だった。同12年3月末、予備役となる。
翌年の正月、北予中理事で伊予鉄道社長の井上要が好古邸を訪れ、校長就任を要請する。当時、北予中は経営も行き詰まり、地元での評判も芳しくなかった。
「国家の大計は人づくりにあります。官立の松山中学校には成績優秀な者しか入学できず、学の志あるおちこぼれが生じます。それをすくいとって、国家のお役に立てる人材に育てるのが本学の建学の精神であります」
どうしてもと言う井上に対し、好古は一言だけ言った。
「こんな老いぼれで役に立つんなら、何でも奉公させてもらうよ。欧米では高官が退職後に社会貢献するのは当たり前になっておる。日本人は少し地位を持って辞めると恩給で遊んで暮らそうという輩が多いが、わしはそういうのは好かん」
この時、好古65歳。校長在任は6年3カ月に及び、その間、一日も休むことはなかった。好古の校長就任で北予中の雰囲気は一変する。(将口泰浩)
秋山好古(中)
登校姿を見て時計の針を正す
2013.6.1 07:44
大正13(1924)年4月に北予中学校長(現愛媛県立松山北高)に就任した秋山好古(よしふる)(1859~1930年)は毎日、同じ道順で同じ時刻に通勤する。「校長の通ふ沿道には、その登校せる姿を見て時間を知り、我家の狂ひ易き時計の針を正すと云はれるほど精確なものであった」と同校理事の井上要は書き残している。
好古の校長就任後、徐々に生徒の身だしなみも整い、目に見えて遅刻や欠席が減り、授業料もきちんと納められるようになった。しかし、好古が生徒を叱ることは一度もなく、怒った顔を見せたこともなかった。ただ登校時30分間、校門前に立ち、あいさつをし、ニコニコと笑顔で校内や教室を見回り、時に落ちているゴミを拾い、生徒たちと経験や教訓を交えた世間話に興じた。
「誠に親むべき好々爺(こうこうや)であった」という。校長室はせまく、夏暑く冬寒い部屋だったが、「暑い、寒い」とこぼすことなく、洋服のボタンひとつ外したこともなかった。
全国の中学校や師範学校などに将校を派遣し、軍事教練を必修とする「陸軍現役将校学校配属令」が大正14年に出される。しかし、好古は「生徒は軍人ではない」として、最小限の訓練にするように指示する。学校職員が好古の軍服姿の肖像を生徒に売ろうとしたこともあった。
いつになく好古は大声で「俺は中学校の校長である。位階勲章など話す必要はない。こんなものを売って生徒にいらぬ金を使わせてはならぬ」と叱り飛ばしたこともあった。
中学校は学びの場であるという信念の下、糖尿病で不自由な足を引きずり、寄付を集め、講堂を建設する。学習環境を整えることも教育者としての使命と考えていた。
住まいは昔の生家で、家事は親類の者が手伝いに来るだけの質素簡潔な生活を続ける。「(日露戦争の)未曽有の大勝利は国難に殉じた戦死者のたまものである。戦死者の遺族に対しお気の毒と存じ、日露戦争後はつとめて独身生活をしている」。教育者となった晩年も、英霊とともに生きていた。(将口泰浩)
秋山好古(下)
4文字に詰まる郷里の感謝
2013.6.8 09:28
「サネユキキトク」の電報が福島・白河に出張していた秋山好古(よしふる)(1859~1930年)に届く。北予中学校(現愛媛県立松山北高)の校長に就任する6年前の大正7(1918)年2月3日。好古は陛下の軍事顧問を務める軍事参議官だった。
周囲が帰京を勧めるが、「すでに弟とは今生の別れのあいさつをしておる」とそっけなく、「イカヌヨロシクタノム」と返電させる。4日早朝には「サネユキセイキョ」の至急電が配達されても「官命を帯びての任務遂行中であり、肉親の死であろうと、私事で帰京はできぬ」と言い放ち、何事もなかったかのように公務を続ける。見かねた部下が陸軍省人事局長と掛け合い、任務交代の陸軍大臣命令が出される。渋々、帰京した好古は、7日の葬儀で葬儀委員長として、あいさつをした。
「兄として、弟を誇れるものは何もありませんが、これだけはお伝えしておきたい。真之は一分一秒たりとも国を思わぬときはなかったと」。参列者のだれもが好古にも感じるものであった。
「前途のため郷里から有能な人物が出るように国のため郷里のために尽くす」。好古最後の使命は教育だった。当分の間という約束だったが、人柄が生徒や教員に浸透するにつれ、人気も高まり入学希望者は3倍に増加、辞任は先送りされる。しかし、その間も糖尿病は悪化、どうにも体がいうことをきかず、昭和5年3月に辞職。同年11月、71年の生涯を閉じる。
6年間一日も休まず登校し、生徒を見守る姿は街中に知れ渡り、時計よりも正確といわれた時間厳守の姿勢はルーズだった街の人
々の意識さえ変える。「無言の教訓、無為の感化は誠に大きいと言はねばならぬ」と北予中理事の井上要は書き残す。
松山でも墓参したいという声に押され、有志の手で道後鶯谷墓地に分墓を建立する。碑には「永仰遺光(えいごういこう)」。永遠に尊敬し、その人徳の光を未来に伝えるという意味だ。最後の使命を全うした好古に対する郷里の感謝の思いが4文字に詰まっている。(将口泰浩)
iPhoneからの投稿